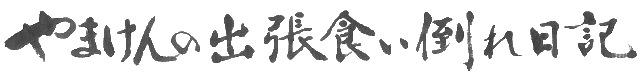
イタリア・ブラ滞在3日目、午前中は待望のピエモンテーゼ牛の視察だ。
実は2018年に、アンズコフーズ社長を務めておられた金城さんと、フランスでど真ん中の肉レストランを成功させている柳瀬シェフらとイタリア・スペインのお肉を視察するツアーをした際に、ピエモンテーゼ牛の中でもブランドとなるFassona(ファッソーナ)の視察にオベルト社に行った。
■世界は広い、そして牛の美味しさもさまざま、ということを識ったピエモンテーゼ牛との邂逅。oberto社が選り抜いたブランド”Fassona”の牛の味とは!? その1 誇り高きOberto社の模様!ゼブ種の血統、ダブルマッスル、未経産36ヶ月肥育! - やまけんの出張食い倒れ日記
https://www.yamaken.org/mt/kuidaore/archives/2018/08/29651.html
この時は、ピエモンテーゼ主の品種の来歴に衝撃を受け、またそれがイタリアの赤身であればあるほどよい肉という食肉格付に合うものであって、日本のような霜降りが上級となる正反対の格付ではありえない性質であることに、なんとも食文化の違いを感じたものだ。
今回は生産者が主体となって創設したラ・グランダという組合に依頼をして、セルジョさんの農園を視察。
■ピエモンテーゼ牛の特性と管理

紀元前からイタリア北部に在来していた白い牛が、パキスタン由来のゼブ種(背中にコブがある、熱帯で生息する牛の品種群)と交配して生まれた品種と言われる。
子牛の色: 生まれたばかりの子牛は小麦色(茶色)だが、生後4ヶ月頃から徐々に白くなる。
去勢されていない雄牛は、首が二重になり、体が黒っぽくなるなど、ボディビルダーのような外見になる。
■農場規模
農場は1895年に設立、セルジョ氏は5代目にあたる。
労働力: セルジョ氏(フルタイム)といとこ(パートタイム)の1.5人で運営。
飼育頭数: 子牛から成牛まで合計約270頭を飼育。イタリアの平均でみて大きな規模ではない。
■ラ・グランダ組合の設立と理念
大規模流通からの脱却を企図して組合を結成。
背景にはおよそ30年前、この地域で大規模な流通業者が小規模農家から不当に安い価格で家畜を買い叩き、零細農家が廃業の危機に瀕していた。
そこで 当時獣医だったラ・グランダ組合の創設者が、スローフード運動が始まったのと同じ時期に、小規模農家を保護し、高品質なピエモンテーゼ牛の生産を持続させるために農家を結集させたのが組合の始まりだという。
■工業的畜産ではなく、自然の循環と摂理を尊重する飼育法を採用

創設時の挑戦として、当時としては「狂っている!」とまで言われたいくつかのルールを設けた。
その一つが母子同一飼育。子牛は生まれた牛舎で母牛と共に育つ。
日本でも通常はそうだが、生後30日未満で母牛から引き離し、他の場所で肥育させるという従来の工業的な方法を否定した。そして 母乳を飲む期間(4〜6ヶ月)は強制的に引き離さず、自然に乳離れするのを待つ。
うーん、それにしても子牛を観ればわかるとおり、バリバリのダブルマッスル、つまりムキムキである。
ダブルマッスルと呼ばれる、筋肉量が通常の1.5~2倍になる遺伝的形質を持っているため、筋肉量(赤身)が多く、その肉質は柔らかい。日本では霜降り度合いが高いほどに価値が高くなるが、イタリアやフランスの食肉格付ではその反対で、霜降りが入ると価値・価格が下がってしまう。ピエモンテーゼの肉質は真っ赤といってよく、日本の和牛のような霜降り肉にはどうやってもならない。このため、日本でもたまにダブルマッスル形質の子牛が生まれるが、高く売れる見込みがないため、淘汰されるのが普通だ。
この辺の違いが興味深い。つまりピエモンテーゼは現代日本の畜産では成立しえない味わいということだ。
■飼料と土壌管理
飼料の地産率がとても高い。もちろん非遺伝子組み換え品種のみを生産する。
大豆不使用を徹底。大豆はピエモンテ州の在来作物ではなく、現在見られるものの多くは遺伝子組み換えであるため、飼料として使用しないとのこと。
飼料の構成:
50%が乾草: 動物の食餌の半分は自家栽培の乾草(ヘイ)、加えて自家農地で栽培されたマメ科牧草(ルーサンなど)。
牧草の自家生産には、NZで多くみられるピボット散水機が使われていた。
これに、可能な限り地域生産された穀物類を自家配合する。 穀物飼料の配合割合はトリノ大学などと連携し、飼料要求率を満たす設計に。単味飼料の形で積んでいるのを、混ぜて給餌している。どうしても地域で穫れないものは他所から持ってくるが、一番遠い飼料供給元がシチリアということで、飼料の地産率が非常に高い。
実は具体的な配合割合も教えてもらったが、ここでは非公開とする。そういえば餌用トウモロコシ(メイズ)は農場周辺でかなりの規模で生産されていた。
■有機認証を超えた「共生農業」
有機認証(オーガニック)は費用を払えば取得できる内容であるものの、ラ・グランダではあえて認証を取得していない。しかし、その基準をはるかに超える取り組みを行っているとのこと。
共生農業(Symbiotic Agriculture): 微生物や小生物によって土壌そのものを豊かにする「共生農業」の認証を取得。化学肥料は一切使わず、牛の堆肥を発酵させた自然肥料のみを使用する。
輪作の実践: 土壌の健康を維持するため、常に同じ作物を栽培せず、トウモロコシや大麦などとの輪作を行う。
生物多様性の維持: 化学合成農薬を使わないことで、土壌の生物多様性を守っている。
■市場での評価と価格
積極的な営業活動は行わず、品質の高さから顧客が自ら求めてくる関係を築いている。規模も大きくないため、スーパーなど小売業者の求めには応じにくく、レストランなど外食業者主体に取引をしている。
一般的な市場価格と比較し平均で3〜4%高い程度の価格で取引されている。もちろんこれは枝肉平均であり、サーロインなどの希少部位は8〜9%高くなるが、組合が一頭丸ごと買い取る方式のため、部位バランスで価格をつけている。
下の写真はハンバーガー用のパティ。レストランのオーダーに応じて厚みや直径を調整している。
■アニマルウェルフェア(動物福祉)
高い評価: アニマルウェルフェアのスコアは非常に高い評価を得ており、政府の外部機関によるチェックも受けている。
出産時の管理: 出産直後の母牛は神経質になることがあるため、母子と作業員の安全のために、授乳室では一時的に鎖で繋がれる。それ以外の場所では完全に自由に過ごす。
子牛の社会化: 子牛は「幼稚園」のような専用スペース(馴致場)に自由に出入りでき、他の子牛と触れ合いながら社会性を学ぶ。母牛は自分の子牛にしか授乳しない。
■肥育期間
ピエモンテーゼ牛の平均的な肥育期間は16ヶ月で、500~600Kgに増体し出荷となる。
ただし、ピエモンテーゼ牛は数多く生産されており、その肥育期間は12~36ヶ月まで幅がある。高級ブランドであるFassona(ファッソーナ)の場合、36ヶ月肥育したメス牛でなければファッソーナとして販売しないという内規があるとオベルト社で聞いた。一般的には肥育期間が長いほど味わいが深くなるといってよい。
日本の和牛の肥育期間は25~40ヶ月と長く、長いほどおいしいと言われる(そのかわり餌代がかかり高価になる)。ピエモンテーゼなぜ16ヶ月といった短い期間で出荷できるのか。おそらくダブルマッスル形質を持ち、赤身の筋肉が1.5~2倍の効率で肥大するため、16ヶ月で600Kgに到達するのだろうと思われる。
■血統の管理と人工授精
DNA登録: すべての牛はDNAサンプルが採取され、100%ピエモンテーゼ種であることが保証されている。
雄牛の選定: 優れた雄牛は精子バンクに登録され、人工授精に用いられる。遺伝的な多様性を保つため、近親交配を避ける管理が徹底されている。
■ラ・グランダ組合の活動
組合員数: セルジョ氏のような農家が63軒集まっている。
情報交換: 毎月1回、全組合員が集まる会議が開催され、経験を共有したり、大学教授から最新の情報を学んだりする機会が設けられている。
コミュニティの絆: 小さなコミュニティであるため、農家同士の結びつきは非常に強く、日常的に助け合いながら農作業を行っている。
さあ、昼食だ!
ラ・グランダの食肉加工場に併設の形で、組合運営のレストラン兼イータリー(!)という施設がある。
ランチはハンバーガー!と大量のポテト。
こちらのポテトは、よくある拍子切りではなく、ポテチ5枚分程度の厚みにスライスしたジャガイモを揚げたもの。これがまたおいしい。
パンプキンの種などが入ったバンズがサックリしていて、これがまたおいしい。そしてパティの肉々しさ、うま味がとても濃い。
このオレンジジュースがまたおいしかった!
ということで、畜産関係者でないとよくわからない内容かもしれないけど、ピエモンテーゼ種の産地視察を二度もできたことで、この品種に対する理解がとても深まった。
一番大きなことは、ピエモンテーゼはうまい!という認識を得たことだ。実は前回の訪問時には、その味に関してはピンと来てなかったんだよな、、、また後ほど書きます。