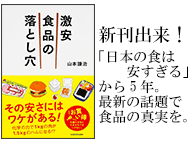中央大学多摩キャンパスでアイドルと会った日。
2004年10月15日 from 日常つれづれ
縁があって、中央大学で開催されている国際インターンシッププログラムで、日本の農業の現実についての講義をしてきた。
びっくりしたのだが、このプログラム、非常に素晴らしい顔ぶれを集めている。スリランカからは、開発プロジェクト「サルボダヤ運動」を実践する団体の人が参加している。僕はこのサルボダヤという思想・運動について学生時代に本を読み、衝撃を受けたことがある。
そして何よりオーストラリアのマックス・リンデガー氏だ。彼は「パーマカルチャー」という農的生活の手法の伝道師で、実存するエコビレッジ「クリスタル・ウォーターズ」の代表的存在だ。持続的農業(化学農法による多投入型農業に対比させた言葉だ)の世界で彼の名前を知らない人は居ないだろう。
僕は学生自体にキャンパスに畑を拓いていたが、その頃「パーマカルチャー」という訳本が出版され、貪るように読んだものだ。そこには農業という営みから、暮らしに関わる全てのデザインが有機的に連関した、刺激的な解説が載っていたのだ。ただ、このパーマカルチャーという手法は固定的なものではなく、その国の風土や気候、そして経済活動のあり方に沿って刻々と形を変えていくものだと思い至った。以来、僕はパーマカルチャーへの憧憬を胸に持ちつつ、日本の現代的農業体系とその傍らで違う道を模索する産直産地型農業の現場へと足を踏み出した。
そのマックスが、僕の講義を観る! こんなに感慨深いことはない。
特別教室にはムンムンと熱気を発散する学生達と、海外からやってきたゲストの皆さんが待ちかまえていた。thinkPadをプロジェクタに接続していると、なんと!背の高いマックスがのっそりと僕の方にやってきたではないか。
「やあ、日本の話をしてくれるので、楽しみにしているよ。」(←というようなことを言っていた)
僕はアガってしまい、「あなたのファンでした。」と伝えるのが精一杯だった。
僕の講演は、日本の農業シーンが今、ダイナミックに変わろうとしている、その流れを体系的に解説するものだ。マックス達のように海外の人に、日本の農業シーンがどのように変わっていこうとしているかを伝えるのは重要なことだ。生産の側面の話、流通の話というブツ切れの解説はあるかもしれないが、農業とは生産だけでは完結しない。流通、食卓まで含めて理解していかなければならないことなのだ。しかしそんなセンシティブな話は公的には発信され得ないからだ。
実際にはパワーポイント40枚程度の図入り解説をしたのだが、簡易版のレジュメを作ったので、関心のある人は観てください。やまけんがどういうコトをやっているのかの一端がわかるかもしれません。
思ったより学生の熱気がすごく、ほとんどが居眠りをしなかった。そして、意図的にショッキングな話(農村の現状)を織りまぜると、ほとんど涙をためているような学生も居た。こういう反応は珍しい。いくつかの大学・高校でこういう話をしたことがあるが、食いついてくる学生は少ない。我が母校である慶應義塾の矢上の講義で話をした時は、ほんとにみんな死んだ魚の眼だった。しかしこの日の中央大学総合政策学部の学生は、素晴らしい反応と態度だった。
講義中、マックスが悲しい眼をしているのが見えた。日本農業が緩慢な死に向かっているという僕の論調に悲しみを受けているのだった。ただ、その後これからをどうするべきかというくだりを聴いて欲しいと思っていた。想いは伝わっただろうか。
終了後、マックスの方から 「Nice speach!」 と手をさしのべてくれた。その後の懇親会では、彼の方から隣に座ってくれ、感動しながら話をした。話の内容はナイショだ。いずれ僕はオーストラリアに遊びに行くことにした。

このスナップは宝物だ。
この素晴らしい講義をオーガナイズしたのは中大の総合政策学部の皆さんで、特に和栗百枝さんという特任講師の存在が大きい。実は僕を呼んでくれたのは彼女で、しんのすけの家でのチャンチャン焼きパーティで紹介してもらい、とんとん拍子で話が進んだ。正直言って、僕の母校である慶應義塾SFCの数倍の熱気があった。拍手とエールを送りたい。
全く食い倒れと関係がない話をしてしまってモウシワケナイが、とても重要な日だったのだ。
ああ、 知を得るとは素晴らしいことだ。久しぶりにアドレナリンが体内を駆けめぐる夜だった。
このWebはいわゆるグルメではありません。味や価格だけではない「よい食事」とは何かを追求するためにひたすら食い倒れる記録です。私の嗜好に合う人しか楽しめないと思いますがあしからず。
本サイトの著作権はやまけんが保持します。出版物・放送等に掲載される場合はご連絡を下さい。トラックバックはご自由に。
・略歴
・農業blog「俺と畑とインターネット」
・食生活ジャーナリストの会
・過去の食い倒れ日記
分類で読む
- blog本(22)
- お取り寄せ(81)
- イギリス(8)
- イベント(250)
- オフ会(69)
- カメラ(216)
- グラスフェッドビーフ(2)
- トルコ Republic of Turkey(41)
- ドライエージングビーフ(34)
- メルマガ(28)
- 出張(1141)
- 口蹄疫(1)
- 口蹄疫を考える(23)
- 宮崎(16)
- 富良野(6)
- 岩手(4)
- 市場人との対話(4)
- 常夏の楽園・沖縄を食べ尽くす(28)
- 日常つれづれ(581)
- 日本の畜産を考える(170)
- 東日本大震災(32)
- 水産物を考える(3)
- 農家との対話(62)
- 農政(17)
- 農村の現実(61)
- 農業の問題(6)
- 陽光の国 シチリアを行く(15)
- 食のエシカル(5)
- 食べ物の本(67)
- 食品偽装問題(2)
- 食材(565)
- 首都圏(485)
月別に読む
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
- 2005年7月
- 2005年6月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 2005年3月
- 2005年2月
- 2005年1月
- 2004年12月
- 2004年11月
- 2004年10月
- 2004年9月
- 2004年8月
- 2004年7月
- 2004年6月
- 2004年5月
- 2004年4月
- 2004年3月
- 2004年2月
- 2004年1月
- 2003年12月
- 2003年11月
- 2003年10月
- 2003年9月
- 2003年8月
- 2003年7月